 |
- 1)
- 「地下水汚染の拡散防止措置に関わる手引き」と「土壌・地下水汚染の総合的な対応に関する指針」の関係性や整合性を確認します。
- 2)
- 法の対象外を含めた汚染事例について検証を踏まえた整理やケーススタディを実施し、合理的な対応方法の考え方を再確認します。
- 3)
- 1)および2)を踏まえて、一般公開用資料の作成と公開方法を検討します。
- 4)
- 会員企業、行政、有識者へのヒアリングや、検討会等を実施して意見交換を行うことで、公開資料の完成度を高めます。
- 活動期間:
- 令和4〜5年度
- 活動の目的:
- 敷地内に地下水汚染が存在することを確認した土地所有者(汚染原因者)が、所管行政や周辺住民と協議しながら地下水汚染の拡散防止措置を自主的に実施するための指針となる手引きの作成を行った。
- 活動の成果:
- 手引きの目的やおおよその手順を示した概要書と詳細な評価手順を示した技術書を作成した。技術書ではサイト概念モデル(CSM:Conceptual Site Model)を活用した地下水汚染状況のモデル化方法、観測井戸の設置と地下水調査方法、地下水モニタリング措置の適用条件、ステークホルダーとのリスクコミュニケーション方法、を主要な項目として記載している。
- 活動期間:
- 令和2〜3年度
- 活動の目的:
- 地下水汚染の合理的な対策を進めるために、発生原因や汚染物質の移動や消長を評価する手法として、「サイト概念モデル(CSM:Conceptual Site Model)構築手法」と「地下水汚染の科学的自然減衰(MNA:Monitored Natural Attenuation)の概念を拡張したモニタリング手法」を発展させ、センター会員が調査・対策時に活用可能な手引案の作成を行った。
- 活動の成果:
- 地下水汚染の調査・対策に関する知見を集約し、地下水汚染に対するサイト概念モデルの適用、観測井戸の設置と地下水調査方法、地下水モニタリング措置、自然減衰の確認方法、数値解析による地下水汚染濃度変化の推定、ステークホルダーとのリスクコミュニケーション、を主要な項目として記載した地下水汚染のサイト評価手法の手引き(案)を作成した。
- 活動期間:
- 平成30〜令和元年度
- 活動の目的:
- 国内おける土壌汚染の評価・対策において、汚染状況や周辺の土地利用状況等に応じた合理的な対策を検討・実現するためには、物質の挙動や対策の効果を適切に説明する科学的な物質移行モデルに基づく評価手法の充実が必要となる。CSM/MNA部会では、平成28-29年度部会でのサイト概念モデル(CSM:Conceptual Site Model)構築手法の調査結果、日本版SR(Sustainable Remediation)評価方法、モニタリング手法の活用検討などの活動成果をベースに、センター会員が調査・対策時に活用可能な評価・管理手法資料の整理と作成を行った。
- 活動の成果:
-
- (1)
- 土壌・地下水汚染の調査・対策方法の立案・合意形成を支援する評価・管理手法を基礎資料として整理した。
- (2)
- CSMの構築により汚染状況及び曝露経路を可視化する手法を整理し、地下水汚染範囲を確定する手順を題材にケーススタディ資料を作成。
- (3)
- 地下水汚染の科学的自然減衰(MNA:Monitored Natural Attenuation)の概念を拡張したモニタリング手法を考案し、具体的な実施手順及びモニタリング井戸の配置と地下水採取方法、汚染地下水のシミュレーション方法、自然減衰の兆候の確認方法、サステイナブルレメディエーションを活用したリスクコミュニケーション方法について技術情報の整理を行った。
- 活動期間:
- 平成28年度〜平成29年度
- 活動の目的:
- 国内おけるリスク評価活用を活性化する上で、評価対象サイトの状況を的確に把握することが必要である。現実の汚染問題では、複雑な地盤や汚染状況に加え、周辺環境への影響の有無や現在および将来の土地利用など、具体的な対策案の検討を進める前の前提条件の整理が重要となる。これら個別サイトの種々の問題を整理するためにはサイト概念モデルの構築が有効であり、海外においても様々なアプローチ方法が検討・活用される。そこで、本WGでは、リスク評価を活用して複雑な日本の土壌汚染問題の解決に寄与することを目的として、「サイト概念モデル(Conceptual Site Model)」の構築に関する海外の最新情報と事例を調査し、新たな評価方法の検討を行った。
- 活動の成果:
-
- (1)
- CSM構築・活用方法に関する文献調査と事例収集
- (2)
- ブラウンフィールド再生事例の文献収集
- (3)
- 日本の土壌汚染対策に有効なCSM構築として、ライフサイクルCSM手法について整理
- (4)
- 日本での土壌・地下水汚染の調査対策事例をベースにライフサイクルCSMの評価手法を適用したケーススタディ3事例を実施し、今後日本におけるCSM活用の課題を抽出した。
- 活動期間:
- 平成28年〜平成29年度
- 活動の目的:
- 「複数の選択肢から最適な浄化工法を選定」するSR手法の検討をさらに進めると共に、新たに原位置浄化推進のための「モニタリング」技術の活用を進めるために、SRの概念を導入した「MNA」の新たな運用方法の検討を行った。
- 活動期間:
- 平成26年度〜27年度
- 活動の目的:
-
前年度部会までに土壌汚染のリスク評価に関するガイダンス(案)、サイト環境リスク評価モデル(SERAM)のマニュアル(案)と計算ツール開発を作成した。本部会では、さらに、これらのガイダンス案および資料、計算ツールを用い、わが国の土壌汚染対策においてリスク評価手法を活用促進する方策を検討し、リスク評価モデルの技術標準化を目的とした検討を行った。
※SERAM(Site Environmental Risk Assessment Model)
- 活動期間:
- 平成26〜27年度
- 活動の目的:
- 土壌汚染対策における新しい取り組みとして、環境的、社会的、および経済的要素の3つを評価して総合的に最適な対策を選択していく「サステイナブル・レメディエーション(SR)」について、欧米でのSRの最新情報や動向を調査するとともに、幾つかのSR評価ツールを用いてわが国の事例に対するケーススタディを実施し、わが国に適用可能なSRのフレームワークの構築(提案)を目的とした。
- 活動の成果:
- 米国および英国の文献調査を行い、わが国における活用方策を検討し、「汚染発生者の視点で最適な浄化方法を選定するコミュニケーションツール」としての有用性を見出した。また、土壌対策に伴う環境負荷を低減するためには、原位置浄化技術の適用機会を増大させることが有用であると考え、日本版SR評価項目の案を作成した。
- 活動期間:
- 平成24年度〜平成25年度
- 活動の目的:
- わが国の土壌汚染対策におけるリスク評価の活用について普及・啓発をはかるため、リスク評価を活用した土壌汚染対策に関する一般住民向けおよび技術者向けのガイダンス案をそれぞれ作成するとともに、リスク評価モデルSERAMの改善・ツール化を行う。
- 活動期間:
- 平成25年度
- 活動の目的:
-
SRの情報収集、国内の適用性・課題の検討
- MNA(Monitored Natural Attenuation)とSRの位置付けの確認
- SRの資料調査等に基づく国内の適用性についての有効性や技術的な課題についての討議
- SRに関する主要な文献の和訳
- 識者との意見交換
- 活動期間:
- 平成22年度〜平成23年度
- 活動の目的:
- リスク評価モデルSERAMの検証、リスク評価の活用のためのガイダンスおよびパラメーターの整備
- 活動期間:
- 平成20年度〜平成21年度
- 活動の目的:
- わが国の土壌汚染対策におけるリスク評価の活用方法の検討、リスク評価モデルの検討
- 活動期間:
- 平成16年度〜平成19年度
- 活動の目的:
- 欧米におけるリスク評価の実態調査、わが国でリスク評価を有効活用するための課題の抽出、欧米のリスク評価モデルの比較
- 活動期間:
- 平成14年度〜平成15年度
- 活動の目的:
- 米国で開発された土壌汚染対策のためのリスク評価モデル(ASTM E2081 : Risk-Based Corrective Action)の調査研究
- 活動期間:
- 令和4〜5年度
- 活動概要:
-
本来、一体として捉えて調査・対策を行う必要のある土壌・地下水汚染への対応が、土壌汚染は土壌汚染対策法、地下水汚染は水質汚濁防止法により連携を図りつつも、個別に運用されてきた実情がある。本部会では、過年度における研究成果等を踏まえ、事業者や自治体担当者等が、地下水汚染と土壌汚染を一体と捉えた調査・対策を進めていく際に参考となる「土壌・地下水汚染への総合的な対応に関する指針(案)」(以下、指針(案)の作成を活動の目的として調査・研究を行った。
- 前身部会における課題及び解決の方向性を検討・整理した。
- 指針の対象を「事業所外地下水汚染発見契機」、「事業所内地下水汚染発見契機」、「事業所内土壌汚染発見契機」とし、それぞれの契機における対応フローを検討した。
- 1,4-ジオキサンを指針(案)の対象物質とし、土壌・地下水汚染の特徴把握および調査方法を検討した。
- 契機別・対象物質別に調査フローを作成し、各調査ステップで必要となる調査項目を検討し、各調査項目における実施内容を「実施すべき項目」、「望ましい項目」、「参考となる項目」に区分して整理した。
- 総合的な対応の計画立案等の参考となる「地下水汚染状況調査Q&A」、「地下水を対象とした対策技術」の検討・整理を行った。
- 総合的な対応事例を本指針の対応フローに沿って整理することで、指針(案)の構成に過不足がないか確認した。
これらの検討結果を踏まえた指針(案)を作成した。 - 活動期間:
- 令和2〜3年度
- 活動概要:
-
土壌・地下水汚染を一体として捉えた総合的な対応に関する調査・対策指針を作成する上で、その課題や方向性を検討すること目的に、以下の調査・研究を行った。
- 自治体における土壌・地下水汚染に関する条例等の歴史や枠組みを調査し、土壌と地下水を一体として進める際の課題を整理した。
- 広域地下水汚染および土壌・地下水汚染を総合的に扱った調査・対策の事例を収集し、グッド・プラクティスとしてまとめた。
- 土壌・地下水汚染に関わる裁判事例を収集し、汚染地下水が敷地外に拡散した場合の法的なリスクについて検討した。
- 土対法第5条および水濁法第14条の仕組み及び両者の関連性を詳細に調査し、現状の法体系における調査・対策の課題についてまとめた。
- 土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針及び同運用基準の内容を精査し、総合的な調査・対策を進める上での課題を整理した。
これらの調査・研究結果を踏まえ、【新たな「土壌・地下水汚染を総合的に対応する調査・対策指針(素案)」】を作成した。 - 活動期間:
- 平成30〜令和元年度
- 活動概要:
- 土壌・地下水汚染の調査・対策について一体化した対応を行うための方策を検討していくにあたっての基礎的な資料収集・整理を目的として活動を行った。活動内容として、(1)土壌汚染対策法の第二次改正内容の整理・課題点の検討、(2)国内の地下水汚染に対する法・条例等の収集整理、(3)国内における大規模地下水汚染の事例収集および原因検討、(4)国内における土壌・地下水汚染を一体化して対応した事例等の収集整理、(5)土壌・地下水汚染の総合的な対応手法の方向性検討を行った。なお、本分科会は、令和2年度以降、自主部会として活動するに先立ち、設置されたものである。
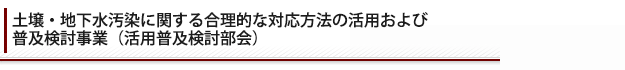
近年、地下水汚染は健康リスクだけではなく、環境面・経済面・社会面の様々なリスクに対応して環境保全を進めることを求められることが多くなっています。そのためには、土壌汚染を主体として考える対策だけでなく、土壌汚染と地下水汚染を一体として捉えて地盤内に汚染が存在していることを理解して、合理的で適切な措置を選択していくことが重要と考えられています。 このような背景から、令和4〜5年度の検討事業では、リスク評価を活用した地下水汚染の拡散防止措置検討部会(拡散防止部会)において、事業所等の敷地内における地下水汚染の拡散防止を行う手順を「地下水汚染の拡散防止措置に関わる手引き」を作成することで整理しました。また、土壌・地下水汚染の総合的な対応に関する指針検討部会(指針検討部会)において、土壌・地下水汚染が確認された場合の事業所内外の連携のあり方を「土壌・地下水汚染の総合的な対応に関する指針」を作成して明確にしました。 本検討事業では,これらの「手引き」および「指針」の内容を踏まえて、双方の考え方をまとめて分かり易く整理し、一般資料として公開することを目指します。その結果、国や地方自治体に対して土壌・地下水汚染を一体として捉えて対応することの必要性が認識され、様々な汚染発見の契機に対して合理的な対応や地域への理解が得られやすくなる社会を目指して活動します。 令和6年度〜令和7年度の2ヵ年で下記の調査・検討を進めています。 |
■土壌・地下水汚染に関する合理的な対応方法の活用および普及検討部会(令和6年度)
高畑陽・塩谷剛・和知剛・佐藤徹朗・土壌・地下水汚染に関する合理的な対応方法の活用および普及検討部会
第30回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会講演集,S4-31(2025) |
|
■リスク評価を活用した地下水汚染の拡散防止措置検討部会(令和4〜5年度) ■地下水汚染のサイト評価手法の活用検討部会(令和2〜3年度) ■CSM・モニタリングを活用した土壌・地下水汚染の管理手法検討部会(平成30〜令和元年度) ■サステイナブル・アプローチ部会 CSM調査WG(平成28〜29年度) ■サステイナブル・アプローチ部会 SR活用WG(平成28〜29年度)
舟川将史・佐藤徹朗・日野成雄・高畑陽・サステイナブル・アプローチ検討部会
第24回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会講演集,S2-2(2018) ■サステイナブル・アプローチ部会 リスク評価WG(平成26〜27年度) ■リスク評価モデルの普及・ツール化検討部会(平成24〜25年度) ■リスク評価方法検証部会(平成22〜23年度) 関するケーススタディ ケーススタディ ■リスク評価活用方法検討部会(平成20〜21年度) −わが国の土壌汚染対策におけるリスク評価の活用に向けて− ■リスク評価活用方法検討部会(平成16〜19年度) −わが国におけるリスク評価活用の概念と課題− −日欧米のリスク評価モデルにおける暴露評価方法の比較− 藤長愛一郎・川辺能成・福浦清・リスク評価適用性検討部会 第13回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会講演集,S1-27(2007) −米国におけるリスク評価の活用事例− −リスク評価モデルの特性比較− −諸外国におけるリスク評価の土壌汚染対策への適用について− ■海外アセスメント・評価調査部会RBCA研究ワーキンググループ(平成14〜15年度)
関連する終了した部会
■土壌・地下水汚染の総合的な対応に関する指針検討部会(令和4〜5年度)
鈴木弘明・北畠義裕・西川直仁・大石力・今安英一郎・土壌・地下水汚染の総合的な対応に関する指針検討部会
第29回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会,S2-14(2024)
佐藤徹朗・嶋本直人・清水祐也・藤安良昌・三原洋一・土壌・地下水汚染の総合的な対応に関する指針検討部会
第29回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会,S3-27(2024)
塩谷剛・中島誠・和田卓也・青木鉦二・佐藤徹朗・土壌・地下水汚染の総合的な対応に関する指針検討部会
第29回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会,S4-12(2024)
佐藤徹朗・鈴木弘明・中島誠・藤安良昌・青木鉦二・土壌・地下水汚染の総合的な対応に関する指針検討部会
第28回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会,S2-23(2023) ■土壌・地下水汚染の総合的な対応に関する検討部会(令和2〜3年度)
塩谷剛・佐藤徹朗・三原洋一・駒崎光俊・瀬野光太・土壌・地下水汚染の総合的な対応に関する検討部会
第27回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会,S3-09(2022)
清水祐也・鴨志田元喜・菅沼優巳・藤安良昌・今安英一郎・土壌・地下水汚染の総合的な対応に関する検討部会
第27回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会,S2-08(2022)
鈴木弘明・中島誠・鈴木洋子・青木鉦二・土壌・地下水汚染の総合的な対応に関する検討部会
第27回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会,S1-09(2022)
中島誠・佐藤徹朗・鈴木弘明・土壌・地下水汚染の総合的な対応に関する検討部会
第26回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会,S7-02(2021)
鈴木弘明・塩谷剛・清水祐也・中島誠・土壌・地下水汚染の総合的な対応に関する検討部会
第26回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会,S5-03(2021) ■土壌・地下水汚染の総合的な対応に関する検討分科会(平成30〜令和元年度)
鈴木弘明・中島誠・菊池毅・日笠山徹巳・門間聖子・土壌・地下水汚染の総合的な対応に関する検討分科会
第25回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会講演集,S4-05(2019) 関連する終了した部会
|



