 |
|---|
| 特別寄稿 「土壌汚染対策法の改正が不動産市場に与える影響を考える」 |
|||
 |
財団法人 日本不動産研究所 環境プロジェクト室長 平 倫明 |
|
|
平成22年4月1日に改正土壌汚染対策法が施行された。土壌汚染対策が「掘削除去」に偏った状況にあることを改めるとともに、汚染土壌の不適正な処理による汚染の拡散を防ぐことなどが改正の背景にある。一定規模以上の土地の形質を変更する場合の届け出も義務付けられた。この土壌汚染対策法の改正によって不動産市場にどのような影響を与えるのか・・・。 土壌汚染地の価値を左右する2つの要素 |
| 「土壌汚染の存在に起因する心理的な嫌悪感等から生ずる減価要因」と定義され、忌み地や事件・事故のあった不動産のように物理的な利用上の阻害はないが、心理的な不安感等から忌避され、市場性が劣る場合などと同様の概念である。 汚染がない場合の不動産価値から、この二つを差し引いたものが土壌汚染地の価値となる(図1)。 図2は、これまでの対策方法に応じた費用・スティグマの関係を示したものである。対策費用とスティグマは表裏一体の関係であり、対策に費用はかかるが、その対策レベルが上がれば、スティグマは小さくなる。これまでの不動産市場で掘削除去が多くみられたのは、リスクが小さく、利用用途が広い不動産が一般に望まれているからであり、だからこそ、対策に高い費用をかけても、より短期で確実に汚染を除去する方法が選択されてきたのであろう。 |
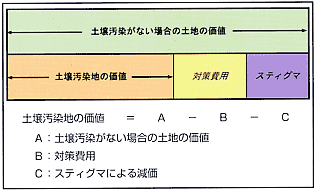 図1.土壌汚染地の価値概念 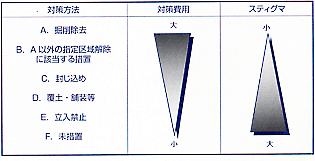 図2.対策方法及用とスティグマび費の関係 |
| 健康被害を生ずるおそれがなければ減価はない? 今回の法改正によって、汚染土壌の搬出を伴わない対策、つまり汚染土壌を残した対策が多くなると言われている。しかし、本当にそのような状況へと向かうのだろうか。たとえば、封じ込めで対応する場合は、対策費用は減るが、土壌汚染は残存する。この場合に封じ込めの対策費用以外は減価はないという取引が市場で受け入れられるだろうか。 法改正の影響を考えるうえで、大きなポイントがここにある。今回の改正では、これまでの「指定区域」が健康被害を生ずるおそれの有無により「要措置区域」か「形質変更時要届出区域」の2つの区域指定に分かれ、要措置区域においては「指示措置」を実施した後は形質変更時要届出区域となる。そして、この形質変更時要届出区域とは、健康被害が生ずるおそれの基準に該当しない、つまり形質変更をしない限りは何らの対策を要しない土地、ということである。では、法で対策を要しないとされた土地は減価がないのか。 土地は、建物の建設など、利用されることが前提であり、この建物の建設にあたっては、建設残土として処理が必要となる搬出土壌が発生することが多い。当然、この土壌が汚染されているならば、適正な処理を求められ、その処理費用は通常の残土処理よりも高額となることが現状であり、その分の費用増が転じて不動産価値の減価となってくる。また、既に建物利用されている土地であっても、将来の建て替え時などにおける搬出土壌の有無と費用増の有無を考えることとなる。 このように、法で対策を要しないとされた土地であっても、「安全性」については一定の評価がされているとみる一方で、土地利用にあたっては「費用性」リスク、すなわち経済的リスクは潜在しているのである。したがって、今後、汚染土壌を残置した土地利用が図られ、ブラウンフィールド問題が解消されていくことが期待されるが、そのような状況のなかでも、汚染土壌の処理費用と通常の建設残土の処理費用が同等とならない限り、土地利用に伴う最低限の経済的リスクを顕在化させる必要性に変わりはないであろう。 行政の「お墨付き」? これまでの不動産市場で自主調査及び対策に係る報告書を管轄行政に受理してもらい、その時の受領印をもって、行政の「お墨付き」を得た、といったコメントを耳にしてきた。また、今回の法改正に伴う新聞記事の中に「形質変更時要届出区域は汚染があっても健康リスクが少ないという行政の「お墨付き」区域である」という表現を目にした。この「お墨付き」、広辞苑で調べるとその意味は「保証」とある。とすると、この場合の「お墨付き」とは何を保証しているのか、市場関係者は土壌汚染に対してどのような保証を求めているのか。 法改正によって、土地の形質変更時の調査が増加し、区域指定される土地も増えることが予想されている。この区域指定については、今回の法改正で2つに色分けされたわけだが、これを旧法と比較してみると、指定区域に指定され、措置命令が発出されるものが「要措置区域」、措置命令を発出する基準に該当しない場合が「形質変更時要届出区域」となる。つまり、区域指定の名称によりこれが明確となったが、その指定のあり方、措置の必要性に係る基準には特段の変化はない。とすると、これまで区域の指定が解除されるレベルの掘削除去が多く選択されてきたことを考えると、区域指定はできれば避けたいという意識は変わらないのではないか。取引する土地について、汚染を残した場合、将来の土地利用においても「安全な土地だ」という行政のお墨付きが得られ、それが市場関係者のリスクをヘッジする機能となるならばよい。そうでないならば、また区域指定により様々な規制がこれまで以上にかかるのならば、区域指定を解除するためにも、掘削除去という費用はかかるものの短期でかつ確実に汚染を除去する手法は改正後も抑制されないのではないだろうか。 今後の不動産市場におけるポイント 今後も、健康被害を生ずるおそれの有無、さらには経済的リスクの観点からも、不動産市場において、土壌汚染の有無を調査し、その状態(3次元の汚染分布や地下水汚染の有無等)を確認していくことは求められることであろう。 一方、今回の法改正では、調査契機が拡大されたほか、(1)搬出汚染土壌の処理の規制が強化され、(2)自然的原因による土壌汚染も法の適用となり、(3)区域指定された区域内の土壌の搬出にあたっては特定有害物質全物質の土壌分析により基準値以下であることを確認しない限りは全てを汚染土壌として処理することとなるが、特に(1)から(3)の3点については、コスト増につながる可能性があるなど不動産市場に与える影響は大きいであろう。 また、一定規模以上の形質変更時の届出に際して、行政による調査命令の発出の基準は、土壌汚染のおそれの基準として条文化されているが、この基準に該当するか否かの判断基準が明確となっていない現状において、管轄行政によってその判断が違ってはこないか、特に自然的原因による汚染懸念に対してはどのような基準で調査命令が発出されるのか。これは、コスト増のほか、建築期間もしくは事業全体のスケジュールに影響を与える可能性がある。 土地利用という観点からいえば、ある程度の予測ができるだけの判断基準が示されること、掘削除去よりも費用がかからない、より短期でかつ確実に汚染を除去する原位置浄化手法が確立することが期待される。一方、汚染土壌を残置する場合に、将来のリスクがヘッジできるだけの「お墨付き」が得られないまでも、土壌汚染対策法が、他の水質汚濁防止法や大気汚染防止法のように水、大気を汚すことを規制する防止法に対し、土壌を汚すことを防止するものではなく、これをもって健康被害を生ずることを防止するために対策を行い、適正に管理をしていく管理法であることを鑑み、残置した汚染土壌の管理のあり方を示すガイドラインが策定され、これに基づく管理を遂行することで、例えば「土壌汚染適正管理区域」の指定を受けるといった適正管理に係る「お墨付き」として区域指定が機能すれば、市場関係者の認識、ひいては社会全体の認識も変わってくるのではなかろうか。 以上、改正土壌汚染対策法施行後から間もない状況で意見を述べさせて頂いた。今後の市場動向を注意深く観察する必要があることは言うまでもないが、今回の法改正は不動産市場の認識を変えるトリガーとなり、汚染土壌は残置され、特段の減価もない方向へいくのか、法適用の範囲が拡がったことで、規制が強化され、これまで以上に費用増といった影響を与えるものとなるのか、みなさんはどのようにお考えになるだろうか。 |
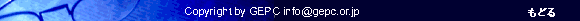 |
|---|