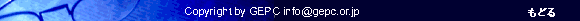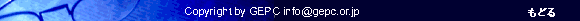著者は廃棄環境と化学物質の視点から、循環型社会を工学的、環境政策学的に研究考察する立場にある。20世紀もあと残すところ数年となった今日、こうした立場から環境を巡る今日的状況を眺めれば、「環境破局」と「共生への光明」が混在した状況となりつつある。より筆者に近い立場で考えれば、「ごみ破局」と「循環への光明」とが錯綜した複雑な状況を呈しつつある。欧米各国より約10年遅れてやってきた危機とも言えようし、より循環への歩みが早まる可能性も秘めている。「ごみ破局」には、埋立処分地制約が待ったなしとなってきていること。豊島に代表される投機跡地問題の顕在化、ごみ焼却におけるダイオキシン問題等の状況を拾うことができる。他にも危機的状況を指摘することはできようが、従来のend-of-pipe的対策に依存してきた産業社会そのものが問われる危機として認識すべき問題である。いずれも、19世紀の産業革命以後に創り、ヒトに限りない便益と夢を与えてきた社会の裏の断面とも言える。しかし、埋立処分地が容易に入手できなくなってきたことは、「限りある地球」が認識される流れの中では当然の流れとも言える。そもそも、比較的均質な処女資源を複雑混合系とした形で、地球に環することのぜ是非を考え、極めて限定的な形でのみ可としなければならないかもしれない。こうした意味では、処分地制約とダイオキシン問題はまさに「ごみ破局」と表現して、おかしくないのである。投機跡地問題は、システムの工夫でもって、まだ対処可能であるようにもみえる。しかし、土壌環境保全に密接に関係すると投棄跡地問題は周辺のヒトや生態にい少なからぬ影響が認められる場合、その修復はまったなしである。
一方、「循環への光明」は言うまでもなく、ごみ減量とリサイクル社会の構築に向けたさまざまな取り組みが現れてきていることである。1991年廃掃法改正でごみの発生抑制、リサイクルが謳われ、1995年には容器包装リサイクル法が成立したことは、まさに21世紀の光明といえる。容器包装のリサイクルスキームは若干のシステム変更はやむを得ないとしてもその基本的考え方は、いずれも全製品に対する普遍的なスキームとならざるを得ないし、これを全産業が取り組むであろう循環管理システムが後押しする。さらに大きな流れとなるであろうことは、グリーンコンシューマと呼ばれる消費者の選択にある。もちろん、こうした流れの不偏化には、紆余曲折はあろうが、地球制約下の経済社会にはこの途しかないように思える。こうした循環型社会への道程が見えはじめていることが最大の光明である。そして、仮に循環型社会が構築されたとしても、いずれは劣化し、再利用不可能となる素材からなる廃棄物の適性管理としての質の高いend-of-point技術は不可欠である。こうした場合には、複雑組成を相手に、より高度に環境保全可能なコントロール技術が必要となる。幸い、こうした処理技術の高度化が進んできている。とくにダイオキシン対策へのチャレンジの中で、欧米、日本では燃焼技術、排ガス抑制、溶融による残査利用、環境検出モニタリング等のフィールドでハイテクノロジー化に成功してきている。また、1997年廃掃法改正では汚染跡地への対処方法として修復基金設立への第一歩が示された。こうした点も破局回避への一筋の光明である。
筆者はこうした現状認識から、いずれ循環資源利用原則を持つべき時期が来るべきと考えています。循環、共生、参加、国際的取組みを基本とする環境汚染も併せて未然防止しなければならない。つまり、二次資源利用と環境汚染の未然防止という二兎を追わねばならないのである。その時期においては、環境資源と土壌環境との関係を考察しなければならない課題が多く出てくる。とくに、二次資源が有するべき性状として、比較されるべきは一次資源性状であると同時に、バックグラウンドとしての土壌性状である。こうした意味から、土壌情報の一層の蓄積とその情報公開が望まれる。かねてより、多くの土壌性状分析が為されてきているはずであるが、その幅広い性状把握をより高精度、広範囲に推進するとともに、後の政策決定に利用可能となるような体系化が待たれる。汚染修復の制度化にせよ、修復基準の設定にせよ、二次資源利用原則を考えるせよ、この土壌バックグラウンド情報が基本となる。以上は、再生資源利用の重要性を意識するがゆえの筆者の見解であり、今後の議論の参考になれば幸いである。一方、従来より環境庁と土壌環境センターにおいて検討を進めておられる土壌汚染浄化に関する検討はますます重要となってこよう、とくに、地域規模から地球規模まで、現世代から次世代までの影響が懸念されるダイオキシン類に対する望ましい土壌のレベルを検討することは危急の課題であろう。
|