 |
|---|
|
〜 特 別 寄 稿 〜 「土壌汚染対策法」の制定に向けて |
|||

|
大阪産業大学 人間環境学部 教授 村岡 浩爾 |
|
|
|
「土壌汚染対策法案」が本年2月15日に閣議決定され、第154通常国会に提出された。3月現在、まさに審議されようとしており、承認されれば9ヶ月以内に施行されるべく関連法令等が整備される。 そもそもこの法案づくりは、平成12年12月の政府行制改革推進本部がまとめた規制改革の見解において「市街地の土壌汚染対策に関する法制化を実効ある制度として検討すべきである」と指摘され、平成13年7月の総合規制改革会議「重点6項目に関する中間とりまとめ」で「土壌汚染の監視・調査手続き、浄化責任、費用負担、情報開示の明確化と実施のための立法措置等を講ずるべき」とされたように、国レベルの要望課題として急がれた仕事である。 土壌汚染の実態状況からの指摘も厳しかった。土壌汚染判明事例数が土壌環境基準が設定された平成3年以降増加の一途をたどり、特に工場跡地等の再開発・売却に伴う土壌調査事例が増加しだした平成8年頃から汚染の顕在化が急増する。このことは健康リスクからくる住民の不安だけでなく、土地取引のトラブルや土地の活用を阻害する国家経済の危機をも招きかねない。次々に起こる問題に地方行政の対応も戸惑いがちである。更に、土壌汚染の修復には総額○○兆円もかかるというような特ダネ的情報も流れた。 このように、土壌汚染に関しては法的ルールがないとも言える状況の中で、環境省は平成12年12月に保全対策の制度の在り方を調査・検討する検討会を立ち上げた。そしてこの検討結果は「中間取りまとめ」として平成13年9月に報告され、これを受けて中央環境審議会土壌農薬部会の中に今後の保全対策の制度を検討する小委員会が設置され、パブリックコメントの手続きを経て今年1月25日にその結果が大臣に答申され、標記法案づくりの基礎資料となったのである。 検討会といい小委員会といい、決してスムースに議事が進んだわけではない。小委員会の委員長を務めた筆者として、この重大な課題に対峙してすべての委員がその法案に向けた合意形成をせねばならぬと実感していたにも拘わらず、各委員が責任を負う分野の立場を考えれば全ての者が公平性を確保しつつ対応するにはあまりにも多くの課題があり、それに引きかえあまりにも短期間で討議を完結せねばならないということが大変苦しいことであったと感じたものだ。 では、どうして、どこに難しい課題があったのか、どのように審議がまとめられてきたか、以下の2点について言及したい。 第1点は、これまで公害として扱ってきた環境媒体の水、大気が公共財であるのに対し、土壌は環境媒体であると同時に土地として利用する場合には値段のつく私財でもある点である。公害なら公法で規定できるのに対し、私有地の汚染は民法上の解釈も加味した上で保全制度を確立しなければならない。本法制度が、重金属や地下水汚染に移行する土壌中の溶出物質によって生ずる土壌汚染が人の健康被害をもたらすことから、国民の健康の保護を図る急務のものであることを誰もが理解しながらも、汚染の状況を把握する調査と健康被害のおそれがあると認める土地の汚染物の除去等措置を、どういう機会に、誰が行い、誰が費用を負担することになるのかが当初の論点となった。結果としては調査を行う契機が明確にされ、調査の実施主体は土地の状態につき責任があり、土地の掘削等の調査を行う権限を有する土地所有者(借地人、管財人もあり得る)であるとされた。土地には所有者があり、汚染された危険な土地を持っている。だから先ずは危険なものを管理している所有者に応分の責任があることから始めようというものである。また、汚染物の除去など土壌の環境リスク低減措置を実施する主体も健康被害の危険性のある土地を現に所有することなどから、一義的には土地所有者とする。費用負担も同様である。ここで二つの問題が発生する。 一つはリスク低減措置のレベルをどの程度にするかということである。汚染土壌を直接摂取することによるリスクは、土地の利用状況に応じた対応を適切に選べばリスクを管理状態におくことができるというもので、土壌のストック型汚染の特徴を捉え、かつ土地の有効利用を維持・促進しうるというものである。地下水等の摂取に関わるリスクでは、周辺地域で地下水が飲用利用等されていない場合にはリスク低減措置の実施は必要ないが、新たな環境リスク発生防止の観点からのリスク管理は行わねばならない。このように土壌・地下水の汚染機構を踏まえた措置の選択を可能にすると同時に、リスク管理の重要性を強調しており、その実行手段として環境リスクが認められる土地は都道府県でリスク管理地として登録され、その台帳は公衆の閲覧に供されることになる。これは次に述べる汚染原因者の特定に関わる問題への関与も含め、地域の汚染土壌の管理に関して都道府県が関与する重要な業務である。 二つ目は当該土地の汚染原因者の立場である。調査およびリスク低減措置をとる実施主体である土地所有者自身が汚染原因者である場合には費用負担等に何ら問題はないが、汚染原因者が別に存在する場合には、汚染者負担原則により、所有者は原因者に求償できる。この場合、過去の汚染行為に対してどこまで遡及できるかが問題であるが法案では一つの見解を示している。また、汚染原因者が存在しない場合や不明の場合は、リスクを抱えかつ土地管理の権限を有する土地所有者がやはり費用負担することになる。しかし、費用負担者が資力に乏しく、現実に費用を負担することが困難であればどうするか。狭い敷地の零細な事業者に費用を負担させること、あるいは中小企業者の宅地兼用型の事業所において廃業時に行う調査はどうするのか、といったことも含めて十分な配慮が必要となる。これには、特殊な技術を要する調査等、またそれに係わる浄化対策で用いられる機器の貸付や融資制度のみでなく、新たな支援措置が担保されなければならず、指定支援法人の設立が予定されている。しかし基金の造成、税制の優遇措置の具体的な検討等は法施行の準備期間の検討に委ねられている。 第2点は、これまでの土壌汚染に係わる法令は、有害物質を含む農産物(具体的には米)の摂取からくる健康リスクにもとづいた「農用地の汚染防止等に関する法律(昭45)」と、土壌を経由して溶出する有害物質が地下水を汚染し、それを飲用することからくる健康リスク対策としての土壌環境基準の設定(平3、平13改)があり、これらに関連して認識せねばならない視点があることである。一つは後者の環境基準で基準項目が増設されてきた背景の中に昭和60年頃からの工場・研究所等の跡地の再開発によって地下水汚染を伴う市街地の土壌汚染が顕在化し、行政上の対策指針として重金属、揮発性有機塩素化合物に関する「土壌・地下水汚染に係わる調査・対策指針運用基準(平11)」が策定されたが、法制度のはっきりしないこの種の土壌汚染に対し、この指針を法的根拠とできない苦しい対応が地方自治体にあったのが今回の法制度検討の発端にもなっていることである。もう一つは「ダイオキシン類対策特別措置法(平11)」の制定である。従来の土壌汚染は重金属等の溶出により地下水汚染となる媒体としての土壌であったが、ダイオキシン類による土壌汚染がその実態の厳しさから、汚染土壌の直接摂取・直接接触による暴露経路が初めて取り上げられたことである。これが今回の検討の前提にもなっている。小委員会では具体的に討議されなかったが、市街地の土地の改変に伴う今後の諸工事時の過程で必ず重要視される事項である。 以上の記述事項に加え、制度の実施までの期間に審議されるべき課題では、技術的課題、さらには油による土壌汚染の問題、自然的原因による汚染の保全のあり方、土地改変によって搬出のある建設残土全般の問題などが考えられる。本制度は、ある意味では科学的な知見ですっきりと解決せず、試行錯誤的で弾力的な対応からスタートせねばならないという緊急性がある。これを考えると、ゼロリスクを理想とするも、これに向かって環境リスク管理を徹底化する重要性が一段と突出してくるようだ。この管理のもとで健康を守って行くことになるという認識を、土壌汚染の直接の関係者だけでなく、一般市民が容易に理解できるようなリスクコミュニケーションが必要であろう。 |
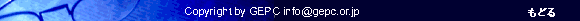 |
|---|